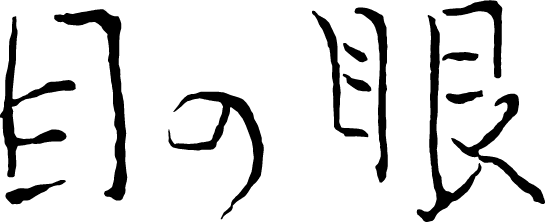展覧会紹介|三井記念美術館 清水眞澄館長に聞く 新円空論とはなにか?
現在、三井記念美術館にて開催中の特別展「魂を込めた円空仏─飛騨・千光寺を中心にして─」は、新たな視点から光をあてた「新円空論」によって円空仏を読み解こうとする意欲的な展覧会。
両面宿儺坐像 千光寺
(画像提供:東京国立博物館 Image TNM Image Archives)
円空は、江戸時代前期に日本各地を巡って修行を繰り返した山林修行僧の一人で、行く先々で木肌やノミ痕を活かした、まるで現代彫刻かと思うような独特の神仏像を残しており、その総数は現在確認されているだけでも5千体を超えるという。
会場風景(内覧会にて撮影)
しかしその生涯や人物像についてはごくわずかな記録が残るだけでほとんどわかっておらず、円空仏の特異な造形と相まって「畸人」と称され、異端な人物として伝えられてきた。
会場風景(内覧会にて撮影)
しかし三井記念美術館の清水眞澄館長によると、山林修行を行なってきた円空にとって樹木は神が宿る神聖なものであり、そこに宿る「樹神」の姿を彫出すことが修行と捉えていたのではないかという。そのため一つ削ってはその神仏の名号を唱え、祈るといった仏教儀式を行いながら彫り進め、その修行の成果として、各地にお像を置いていったのではないかと推測する。決して、世話になった現地の人々のお礼として、という軽いものではなかったようだ。
また円空仏は、寄木造りが主流となった日本の仏像彫刻史のなかでは異端として捉えられがちだが、実は奈良・平安の頃から記録に遺る「立木仏(たちきぶつ)」の流れに沿うものとして位置付けられるものだとのこと。立木仏とは、木材を彫刻の素材として整え乾燥させてから使うのではなく、自生している樹木を生木のまま彫り出す技法のことで、円空が彫刻史からみても異端でないことがわかるという。
会場風景(内覧会にて撮影)
また円空は彫刻以外にも、経文や仏教儀式についても膨大な研究を行っている学僧であり、また和歌集を残すほどの歌僧でもあったいう。
そうした背景を踏まえ、本展では従来のような「時代別」「地域別」ではなく、円空が表現しようとしたテーマに合わせて展示構成を行い、新たな光を当てようとしている。
この記事では清水館長に直接、本展の見どころを解説していただいた動画を紹介するので、ぜひ会場で円空仏の魅力に触れていただきたい。
〈展覧会情報〉
特別展「魂を込めた円空仏─飛騨・千光寺を中心にして─」
会場:三井記念美術館(東京都中央区日本橋室町2丁目1−1 三井本館 7階)
https://www.mitsui-museum.jp/
会期:2025. 2月1日(土)〜 3月30日(日)
開館時間:10:00~17:00(入館は16:00まで)
休館日:月曜日(但し2月10日、2月24日は開館)、2月23日(日)
入場料:一般 1,500(1,300)円/大学・高校生 1,000(900)円/中学生以下 無料
- 70歳以上の方は1,200円(要証明)。
- 20名様以上の団体の方は( )内割引料金となります。
- リピーター割引:会期中一般券、学生券の半券のご提示で、2回目以降は( )内割引料金となります。
- 障害者手帳をご呈示いただいた方、およびその介護者1名は無料です(ミライロIDも可)。
お問合せTEL:050-5541-8600 (ハローダイヤル)
*雑誌『目の眼』の関連バックナンバーもあわせてご覧ください。
目の眼2013年4月号「円空の微笑みと白」