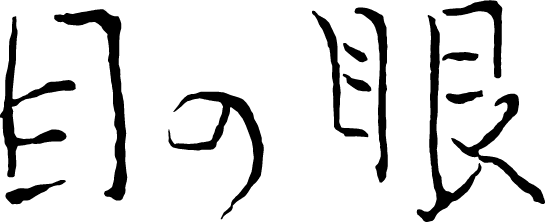台湾・台北市にある国立歴史博物館をご存知でしょうか。1955年に設立され今年で70周年。5万点以上の絵画、陶磁器、青銅器、玉器、家具や人形など古今東西の文化財が収蔵されています。建物は中国宮殿様式の鉄筋コンクリート。2024年に修復工事が完成し、リニューアルオープンしています。
台北駅から地下鉄の淡水信義線に乗って2駅。中正紀念堂駅で降り、南海路をまっすぐ10分ほど歩くと、台北植物園に隣接した国立歴史博物館に到着します。

2月に台北を訪れた際、「藏珍—清翫雅集30周年記念コレクション展」が開催されていると聞き、観覧してきました。
「清翫雅集」は1992年に設立された台湾のコレクターグループ。明代の書籍『清翫』から名付けられたそうで、「清翫」は「学び鑑賞する」という意味、「雅集」は風雅なことをする会、趣味の会のことです。メンバーは正会員32名、名誉会員2名、これまで360回以上の会を開き、図録集の刊行や展覧会の開催など、積極的な活動をしてきたそうです。
国立歴史博物館での展覧会は、過去に「中華文物集粹」、「20周年記念コレクション展」を開催しており、今回で3度目。10年ぶりの展覧会ということになります。
展示されている美術コレクションは、古代から現代まで、多岐に渡ります。絵画、書、陶磁、玉器、漆器、仏像といった中国の美術工芸、さらにバスキアや草間彌生など今最も注目されている作家を含むコンテンポラリーアート、台湾の現代美術作家の絵画彫刻作品など、コレクターの鋭い眼、趣向によって選ばれた美術品の数々が展示されています。

陶磁器
1階会場に入ってすぐ正面には、世界最高峰の磁器が作られた中国の名窯・景徳鎮の官窯でつくられた清時代雍正・乾隆年製の天球瓶が3点も展示されていました。
天球瓶とは、球のように丸く膨らんだ胴から名付けられたもの。展示されている天球瓶には、粉彩という鮮やかな彩色で、桃や吉祥文が美しく描かれています。
海外オークションで天球瓶は落札額10億円以上を記録したものもあるほど、世界的に評価が高い逸品です。
この展覧会を詳しく紹介しているYouTubeチャンネル「戴忠仁的新國寶檔案」を運営している戴忠仁さんはこの展覧会に展示されている美術品は総じて400億新台湾ドルの価値があると紹介されています。日本円にすると、およそ2000億円 !? 「清翫雅集」が世界トップクラスのコレクターグループである事が分かります。

天藍釉長頚扁瓶 一対 清・雍正年製 景徳鎮 高31㎝
天球瓶と並んで、美しいスカイブルーをした頸(くび)の長い瓶がありました。清の雍正年製(1723〜1735)に景徳鎮でつくられたものです。天藍釉(てんらんゆう)という空色の釉薬がたっぷりとかけられています。まっすぐに伸びた頸とバランスのいいフォルム。しかもそれが一対で展示されていると、その見事な造形力に思わずため息がでます。

青花海波花唐草文扁壺 明・永楽年製(1403〜1424) 景徳鎮 高39.8㎝
また中国では青花、日本では染付というブルー&ホワイトの磁器も、白地に青いコバルト顔料で描かれた文様の繊細さが際立って美しく、お好きな方が多いと思います。
上掲は扁壺(へんこ)という胴が平たい壺。立たないので台の上に傾けて展示されています。よく見えず申し訳ないですが、上部に頸がついています。面白いのは、ご覧のように胴の中央に丸い突起があって、そこだけ波文が描かれていること。周囲は花唐草文で規則正しく波文の突起を囲んでいます。この器形はイスラム13世紀ごろの金属器を模したもので、輸出用に作られたのではないかと考えられているそうです。

左:灰釉加彩馬 北魏時代(386〜535年) 高27㎝
右:緑釉犬 漢時代(紀元前260〜220年) 高33.7㎝
古代中国では、亡くなった人が生前と同じように地下世界で暮らすと考え、人や動物、家や家畜、家財道具のミニチュアなどをつくり、お墓に納めました。それらを明器(めいき)といい、陶で作ったものを俑(よう)といいます。
日本にも戦前から、俑がたくさん中国から入って、愛好家たちが賞翫してきました。
上掲の犬と馬は、漢時代のワイルドな造形、北魏時代のシャープなライン、それぞれ最大限に良さが表現された逸品です。

白磁刻花牡丹文水注 北宋時代(960〜1127) 定窯 高17.8㎝

白釉刻花猫蝶文花葉形枕 北宋時代 磁州窯 高5.5㎝
北宋時代は中国陶磁の黄金時代と呼ばれています。本展でも定窯の澄んだ白磁や南宋時代龍泉窯の鮮やかな青磁の逸品が展示されていました。
どれも刻まれた文様がシャープだったり、把手に凝った装飾が施されていたりと、見どころがあるものばかりです。
個人的には、猫と蝶が描かれた磁州窯の陶枕(とうちん 陶器で作られた枕)が愛らしくて魅力的でした。
猫を描いた東洋陶磁は少ないので、その点から言ってもとても貴重な逸品だと思います。

青花胭脂紅彩花唐草文水瓶 一対 清・乾隆年製(1736〜1795) 高19.4㎝
胭脂紅彩(えんじこうさい)とは、西洋から伝わった輸入の紅色の顔料を釉薬の上に描いたものだそうです。日本でよく見る釉裏紅(ゆうりこう)とは釉薬の下に赤い顔料で描いていて、技法から見ても異なるそうです。上掲の作品は青色でも描いているので、青花胭脂紅彩。
歴史博物館でいただいたパンフレットには、「青花胭脂紅彩纏枝蓮紋賁巴壺」とありますが、日本でわかりやすい名称にしました。(※他作品も同様)
賁巴壺は、乾隆帝が寺に供物を捧げる際に使用した供物容器だそうです。
西洋風な雰囲気も感じられる清・乾隆時代の華やかな名品です。
仏教美術
次は仏像を観ていきたいと思います。大きな仏像が1,2階の展示フロアの要所要所に展示されています。
北魏時代(386〜535)の石彫の菩薩頭像や唐時代(617〜907年)の金銅仏、有名な天龍山石窟や雲崗石窟の石仏など、古い時代の仏像もとても見応えがありましたが、宋金時代から元明時代にかけての木彫仏や金銅仏の表情や姿が端正で、美しく、これまであまり見た事がなかったため、引き込まれました。
宋から明にかけての仏像は日本では見ることが少ないので貴重な機会だと思います。

左:伎楽天像 石彫 北魏時代 龍門石窟
右:大勢至菩薩頭像 石彫 唐時代 雲崗石窟

木彫菩薩立像 宋/金時代 高111㎝
さらに、11〜12世紀の大理国、15〜16世紀の西蔵(チベット)の金銅仏も独特です。
大理国は聞き慣れない国名ですが、少しネットで調べたところ、937年に現在の雲南省大理市を首都として中国南西部に樹立された多民族政権だそうです。ベトナム北部にまで領土を拡げたほど強大な国となりましたが、1254年にモンゴルに滅ぼされたとありました。仏教を篤く信仰し、国王は退位すると出家して僧侶となったそうです。仏像にも威厳を感じます。

金銅四臂(しひ)観音菩薩坐像 11〜12世紀 大理国 高38㎝

鍍金四供養天女彫刻飾板 15世紀 チベット・丹薩替寺 高(蓮座)46㎝

金銅仏の展示風景

蓮托金舎利塔 晩唐時代 高22㎝
また珍しい逸品として、唐時代の舎利塔も見逃せません。舎利塔は仏陀の遺骨(舎利)を納める塔のこと。お寺にある三重塔や五重塔も本来は仏陀の舎利を納めるための塔。
仏陀が亡くなった際、その遺骨は分骨されてインド各地の寺に納められ、後年にさらに細かくされて分けられたそうです。
後世になって、中国の僧などが仏舎利が納められた塔の前で供養した宝石の粒などを仏舎利の代わりとして舎利塔に入れて持ち帰ります。
そのため、舎利塔や舎利容器が大きさや素材も様々に無数に作られました。
展示されている舎利塔は銀鍍金で、蓮花に塔が乗った非常に豪華なもの。手前左は塔に納められていた舎利壺、右は蓮の花の中に入れられていた天部像で、塔を支えるようなしぐさをしています。
玉器


玉器展示風景
中国は古代から、玉を神聖な力を持つものと考え、珍重してきました。祭祀や弔いに用いるもの、権力のシンボルとして、様々な玉器がつくられています。緑の玉はネフライトという軟玉です。
鮮やかなグリーンや透過性をもつ白い玉に超絶技巧な彫刻を施したものが多数展示されています。その他にも、玉を用いて作られた古代の動物たちやカップなどはプリミティブでシンプルな造形と玉の滑らかさや色彩に時間を忘れて見入ってしまいました。
他にも、書画、文房具、漆器、七宝、竹工芸と名品の数々が展示されています。会期は3月23日までと、まもなく終了ですが、素晴らしいコレクションの一端をレポートさせていただきました。
「清翫雅集」コレクションを通じて中国美術の魅力をより一層感じることができる展覧会です。
おわりに
国立歴史博物館にもし行かれることがありましたら、隣接する台北植物園を通り抜けていくのがおすすめです。日本統治時代に始まったという100年以上の歴史をもつ広大な植物園は入場無料。(その場合は小南門駅で降りると植物園が近いです)
植物園の中には、かつては茶店だったという昭和初期に作られた日本家屋「南門町三二三」と小さな日本庭園もあり、整備されていて観覧できます。
鳥の鳴き声を聞きながら、ゆっくり散策していくと、国立歴史博物館の赤い建物が蓮池の向こうに見えてきます。季節によっては美しい蓮花が楽しめるでしょう。白い鷺が翼を休めていたり、巣作りのリスが人を恐れることなく駆け回ったりしているのも心和みます。


歴史博物館4階には、新しくてきれいなレストラン「荷悦」があり、植物園を眺めながら食事やお茶を楽しめます。


レストラン「荷悦」 窓から植物園が眺められる。

台湾牛肉麺
他にもメニューが多く、ランチができます。
このエリアは「南海学園」と言って、他にも総統府など日本統治時代の古い建築がある歴史的な地区でもあります。半日ほどゆっくり時間をとって散策すると楽しいスポットです。台北旅行の際はぜひ寄ってみてください。
(目の眼編集部 小林后子)
「藏珍—清翫雅集30周年記念コレクション展」
会 場:国立歴史博物館1階・2階展示室
所在地:台湾 台北市南海路49号
会 期:2025/01/17 ~ 2025/03/23
開館時間 火曜日〜日曜日 10:00〜18:00(毎週月曜日は休館。祝日やイベント開催時には別途告知あり)