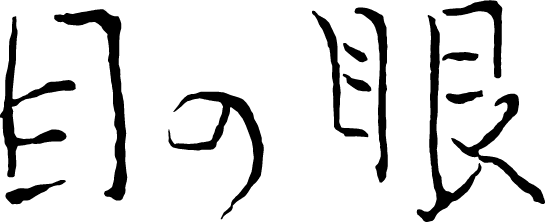神奈川県立金沢文庫 特別展「運慶 女人の作善と鎌倉幕府」開催中
神奈川県立金沢文庫では、2025年2月2日(日)まで、特別展「運慶 女人の作善と鎌倉幕府」が開催中です。貴重な運慶の真作、大威徳明王像(重要文化財)とともに、限りなく運慶に近い運慶工房、慶派の仏像が堪能できます。

神奈川県立金沢文庫 正面入口

展示風景
1.金沢文庫の歴史
「金沢文庫」とは、鎌倉時代に北条実時(ほうじょうさねとき1224〜1276)が創設した現存する最古の武家文庫です。
神奈川金沢文庫は中世歴史博物館として1930年に創設され、1990年に「金沢文庫」があった場所に移転しました。
館の東側には尾根を挟んで古刹称名寺があり、鎌倉時代に称名寺から金沢文庫への通り道だった隧道(ずいどう)が残っています。現在はその脇に作られたトンネルを抜けたところが正面入口です。

実時は、大河ドラマ「鎌倉殿の13人」でもご存知、鎌倉幕府を盤石なものにした二代執権北条義時の孫にあたります。三浦半島の東京湾側の付け根にあたる金沢を所領としていたため、金沢北条氏と称されます。
称名寺は実時が1258年に建てた持仏堂を1267年に真言律宗の寺院として開山したもので、金沢北条氏の菩提寺でした。

称名寺境内
1333年に北条氏一門が滅亡し、鎌倉幕府が倒れたのちも存続し、「金沢文庫」を管理していましたが、室町時代以降、蔵書の多くは散逸します。
しかし伊藤博文などによって明治以降に回収された文書や称名寺の聖教類など貴重な中世史料があり、国宝に指定されました。
現在、聖教をはじめ、称名寺に遺された史料や仏像などの仏教美術は、神奈川県立金沢文庫に寄託され、保存研究されています。
2. 金沢文庫と運慶のかかわり
2007年に、称名寺の子院である光明院が所蔵する大威徳明王(だいいとくみょうおう)像の保存修理に伴い、像内納入品が見つかりました。その中のひとつ、お経を書いた巻物「大威徳種子等及梵字千手陀羅尼」の奥付に運慶の名が記されていたのです。
このことにより、光明院の大威徳明王像は運慶の真作であることが確定し、重要文化財に指定されました。

大威徳明王像 運慶作 建保四年(1216) 神奈川・光明院 重要文化財

3. これまでのイメージとは異なる運慶の側面
今回の運慶展は神奈川県立金沢文庫としては4度目。
さらに深く運慶の実像に迫るテーマとして、光明院の大威徳明王像が、大弐局(だいにのつぼね)という鎌倉幕府二代将軍・源頼家、三代将軍・源実朝の養育係を務めた女性の発願であったことに着目し、「女人の作善(さぜん)」にスポットを当てています。
ちなみに「作善」とは、寺や仏塔、仏像を建立したり、写経や供養をしたりといった善い行いをする事。人々は様々な祈願や極楽往生のために、作善を行いました。
展覧会を担当された主任学芸員の瀨谷貴之さんは、
「運慶のイメージとして、美術ライターの橋本麻里さんが端的に“マッチョ”と言われていますが(笑)、これまで東国武士との結び付きや東大寺南大門の仁王像の力強い豪放な作風から「男性的」な仏師という印象でした。ところが大威徳明王像の像内納入品が発見されたことで、北条政子や大弐局といった女性施主の存在がクローズアップされてきました」
と、戦に明け暮れる夫に代わって、あるいは率先して「作善」を行っていた女人たちと運慶の関わりを取り上げたそうです。
4. 曹源寺の十二神将
運慶が率いた仏師集団、運慶工房の制作とされている横須賀・曹源寺の十二神将像は、現存していない鎌倉・永福寺(ようふくじ)の薬師堂に安置されていた十二神将を模刻したものと考えられています。

十二神将立像 鎌倉時代 神奈川・曹源寺 重要文化財
永福寺は1192年(建久3)から1194年にかけて、源頼朝の発願により建立された大寺院で、薬師堂の願主は北条政子でした。その目的は1192年8月6日に生まれた実朝の安産祈願もしくは誕生報謝だったと考えられ、永福寺の仏像制作は運慶に依頼された可能性が高いそうです。

鬼瓦(永福寺出土)鎌倉時代 鎌倉市教育委員会
曹源寺の十二神将は、像内の修理名に建久年間に作られたと書かれていること、さらに鎌倉時代の歴史書『吾妻鏡(あづまかがみ)』に、実朝が生まれる際に安産祈願をした寺のひとつとして宗元寺(曹源寺)が書かれていることから、運慶が永福寺の十二神将を制作して間もない時期に、永福寺の十二神将を規範に運慶工房で作られたと推定されるそうです。
十二神将は十二の方角を守る護法神で、仏の中の天部(てんぶ)に分類されます。十二支に当てはめて、それぞれ干支の動物を頭部につけていることが多いです。
曹源寺の十二神将は、巳年の神将が他の仏像よりもひときわ大きく制作されています。近年、安産を祈願した実朝が巳時に生まれたためではないかと言われています。

十二神将立像のうち巳神 鎌倉時代 神奈川・曹源寺 重要文化財
他の神将もふくめ、運慶真作である浄楽寺の毘沙門天立像に作風が近いことからも、運慶が率いていた時期の運慶工房作と考えられる貴重な仏像です。
5. 運慶願経
本展覧会では、運慶自身が発願したという京都・真正極楽寺(しんしょうごくらくじ)所蔵の法華経(運慶願経)が展示されています。
奥書によって1183年に制作されたことがわかるもので、そこには願主僧運慶の名とともに、「女大施主 阿古丸」と書かれており、運慶の妻と息子(湛慶)の幼名と考えられています。

『法華経』(運慶願経) 寿永二年(1183) 京都・真正極楽寺 国宝
「発願と制作には、運慶とともに、妻が関わっただろうと思われます」と瀨谷先生。ここでも女性の存在がクローズアップされています。
ちなみに、当初、仏像制作の工房は寺院に付属し、僧が制作を行っていました。特定の寺院以外の仕事をするようになってからも、仏師は出家するのが慣例でした。そのため、運慶は妻子をもつ仏師であり、僧でもありました。
6. 運慶作と運慶工房作
運慶といえば、日本の歴史上もっとも有名な仏師ですが、実際に運慶作と確定している作品は、大威徳明王像を含め6件のみです。
- 国宝 奈良・円成寺(えんじょうじ)大日如来坐像 1176年
- 国宝 静岡・願成就院(がんじょうじゅいん)阿弥陀如来坐像、不動明王及び二童子立像、毘沙門天立像 1186年
- 重要文化財 神奈川・浄楽寺 阿弥陀三尊像、不動明王立像、毘沙門天立像 1189年
- 国宝 奈良・東大寺南大門 金剛力士立像 1203年
- 国宝 奈良・興福寺北円堂 弥勒如来坐像、無著(むじゃく)・世親(せしん)菩薩立像 1212年頃
- 重要文化財 神奈川・称名寺光明院 大威徳明王像 1216年
瀨谷先生にお話を伺うと、「運慶作とするか、運慶工房作とするかは、研究者によって意見が異なる場合もあります。運慶は棟梁として、多くの小仏師を使って制作を行っていました。重要な依頼で自らも制作に関わった仏像に限って自身の名前を記銘したとも考えられます」と、運慶工房とされている仏像の中にも、限りなく運慶に近い作品があり、単純に運慶作か否かではなく、さらにきめ細かい運慶研究がされるようになってきたそうです。
7. 京都に見られる運慶に近い仏像
本展覧会に出品されている目玉のひとつ、京都・清水寺の観音・勢至菩薩像もまた浄楽寺の阿弥陀三尊の作風に近く、1189年頃、若き運慶が関わる工房での制作かもしれないそうです。


観音・勢至菩薩立像 鎌倉時代 京都・清水寺 重要文化財
その隣に展示されている個人蔵の勢至菩薩坐像も作風がよく似ています。「これは持ち主の方が、運慶作と目されている半蔵門ミュージアムの大日如来坐像に似ていると仰っていましたが、私はひと目みて清水寺の観音・勢至菩薩を思い出しました」と瀨谷先生。
「運慶は興福寺に所属していた奈良仏師ですが、やはり京都の寺院の仏像依頼が多かったことでしょう。そして北条政子の父・時政の後妻である牧の方は興福寺と関わりがありました。運慶にとって東国武士との最初の仕事となった願成就院の造仏は時政の発願でした。ここから源頼朝・北条政子につながり、気に入られたのかもしれません。さらには、頼朝の寄進により再建した奈良・東大寺、興福寺の仏像制作を任され、都での評価もあがったのではないでしょうか」

勢至菩薩坐像 平安~鎌倉時代 個人蔵
8. 「運慶」を規範に作られた仏像群
本展では、「大仏殿様」と呼ばれる京都・海住山寺の四天王立像(重要文化財)、伝毘沙門天立像(個人蔵)が展示されています。

四天王立像のうち持国天・増長天像 鎌倉時代 京都・海住山寺 重要文化財
(展示期間:)12/6〜1/18

伝毘沙門天立像(大仏殿様四天王像のうち広目天)鎌倉時代個人蔵
「大仏殿様」とは東大寺大仏殿に安置されていた四天王立像を規範として造像されたと考えられる四天王像を称しています。
東大寺大仏殿の四天王像は、「建久7年(1196)に、康慶が運慶、快慶、定覚(じょうがく)をはじめとした慶派一門を率いて再興造像が行われた」もので、現存はしていませんが、醍醐寺所蔵の「東大寺大仏殿図」によって、どんな像であったかが詳しくわかるそうです。
海住山寺の四天王立像は作られた際の彩色が残るすばらしいものです。2体ごとに展示されていますが、12月21日から1月18日までは4体そろって展示されているので、この期間が一度に観覧できるチャンスです。
9. 伝説の仏師「運慶」
運慶は、鎌倉時代からすでに伝説の仏師でした。神奈川・光触寺所蔵の「頬焼阿弥陀縁起絵巻(ほおやけあみだえんぎえまき)」(鎌倉時代・重要文化財)では、奇跡を起こした阿弥陀如来像を造った仏師として雲慶(=運慶)が登場します。

頬焼阿弥陀縁起絵巻 鎌倉時代 神奈川・光触寺 重要文化財 1月18日~2月2日展示
こうした説話からも、運慶が奇跡を起こすほど素晴らしい仏像を作る仏師として、早くから尊崇されていたことがわかります。
このほかにも、運慶の父・康慶が1177年に造像した地蔵菩薩坐像(静岡・瑞林寺 重要文化財)から、南北朝時代の大仏殿様の変形といわれる四天王立像(個人蔵)まで、展覧会タイトルにある「女人作善」についてはもちろん、運慶作とは何かを知ることもできる充実した展覧会です。

展示風景
ボランティアによる展示解説や講座もあって、より運慶と鎌倉時代の仏像について知ることができます。
ぜひ風光明媚な金沢文庫へ出掛けてみましょう。
〈展覧会情報〉
特別展「運慶ー女人の作善と鎌倉幕府」
-------------------------------------------
参考文献:『運慶と鎌倉』
神奈川県立金沢文庫・横須賀美術館編
2024年11月刊 吉川弘文館 2200円+税
*今秋開催された横須賀美術館・鎌倉国宝館・神奈川県立金沢文庫による3つの運慶関連の展覧会の公式図録です。
-------------------------------------------
雑誌『目の眼』の関連バックナンバーもあわせてご覧ください。
▷ 連載〈ほっとけない仏たちスペシャル「運慶」〉前後編